“服従”が“思考停止”となるとき〜評:工藤信夫
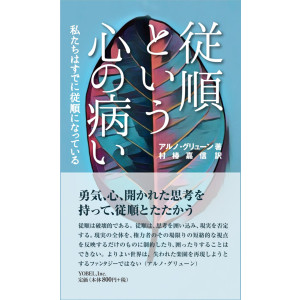 評:工藤信夫(くどう・のぶお=平安女学院大学名誉教授、精神科医、医学博士)
評:工藤信夫(くどう・のぶお=平安女学院大学名誉教授、精神科医、医学博士)
アルノ・グリューン著 村椿嘉信訳
『従順という心の病い―私たちはすでに従順になっている』
〝従順〟が良しとされる文化と、信仰の世界に再考を迫る、すぐれた洞察の書である。
著者はユダヤ人の両親のもとに生まれ、米国に移住、精神分析医として名高いテオドール・ライクの下で指導を受け、チューリッヒで精神療法家として開業された経緯の持ち主であるから、当然ナチスドイツのホロコースト(大量虐殺)からポルポトの暴力、虐待に至る心理機制を理解した上での執筆と考えられる。
私共が注目したいのはこの心理機制と、宗教者に求められた〝従順という徳〟はカルト問題にも通じる病理である、という著者の指摘である。
例えばフロイトの娘、アンナ・フロイトの打ち出した〝攻撃者との同一化〟は暴力的な時代の人間に広く認められる心理機制だと著者は言う。
圧倒的な力を持つ支配者の恐怖の下に置かれると、無力な人間は生きのびるために、攻撃者との同一視を余儀なくされるのみならず、その人自身が攻撃者となり、より弱い者を攻撃するという暴力、虐待の連鎖が起こされる。
例えば母親から虐待されて育った子供は、自分を母親と同一視することによって、母親に対する不安を解消し、自分自身に対する屈辱感や劣等感を、さらに弱い立場の者を攻撃して、その不安を解消しようとするという。
そしてこの機制は今日のグローバル化する時代の暴力に符号するともいう。
というのもそれは〝愛と共感〟〝いたわり〟による連帯を土台とするのではなく、強権やまちがった権威、権力で人を脅し、操作をしようとするからである。
この点現代社会は、人々に〝適応〟を強要することによって、安定を計ろうとするがそれは〝見せかけの適応、従順〟でるが故に、隠された病理である。
その根底にはその人自身の自己否定、自己嫌悪、劣等感があるからである。
長い間、日本の教会と信徒の心の病理に注目してきた評者にすれば〝従順〟を良しとしてきた日本人の信仰心には、多分に〝服従〟という美名のもとに〝思考停止〟という要素が入り込んでおり、この力は足並みのそろわないものを排除して〝均一化〟を求める日本の教会が思い浮かんでくる。
日本人の信仰を吟味する、再生の書と言ってよい好著である。
2017.02.26発行 「クリスチャン新聞」に掲載。


