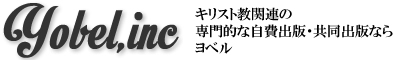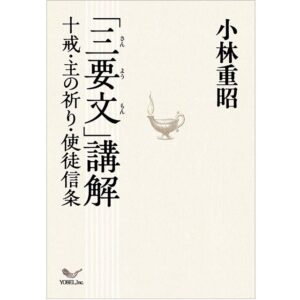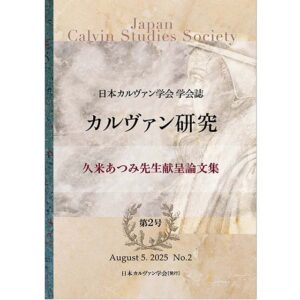大貫 隆[著]福音書の隠れた難所
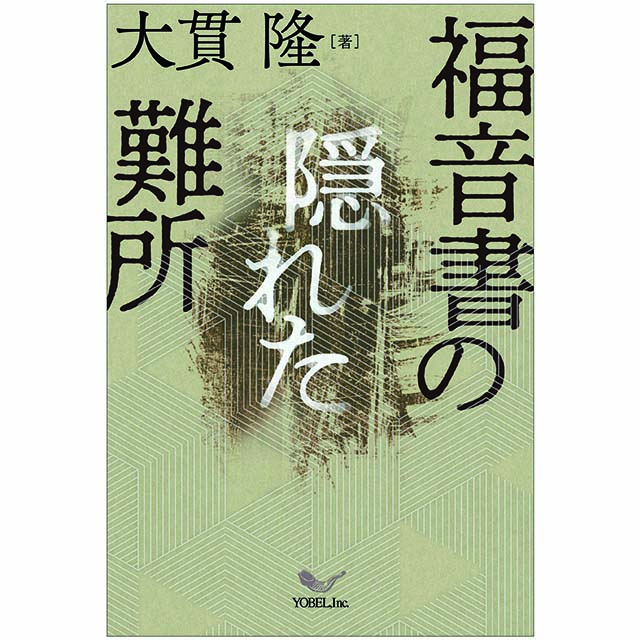
大貫 隆[著]福音書の隠れた難所
四六判上製・416 頁・本体2,800 円+ 税 ISBN978-4-911054-63-5 C0016
書 評
旅に難所はつきもの。
超えてこそ見える絶景!
イエスはなぜ禿鷲と死体を語るのか。ナゾラ人とは何者か。自身を「食い物」にせよとの人肉嗜食発言(ヨハネ福音書)はどう解すれば良いか……。福音書に立ちはだかる5 つの「難所」を取り上げ、研究者生涯を傾注して取り組んできた成果が結晶!
付録 荒井献の学術研究 ― その功績と遺された課題
(福音書には)私自身が日本語にどう訳せばよいのか常に頭を悩ませてきた箇所がいくつかある。それぞれが一体どういう理由で難所になるのか、またどういう解答が考えられるのか、積年の宿題を果たすつもりで、改めて考えをまとめ、書き下ろしてきた。本書はそこから生まれた合計五つの論考を集めたものである。(本書「序」より)
主な目次
第一章 人の子と禿鷲
― マタイ福音書二四章節/ルカ福音書一七章節によせて
要 旨
はじめに― 先行研究と本章の課題
Ⅰ 禿鷲の言葉(マタイ二四/ルカ一七) ― 元来独立の格言
1 研究史と未決問題
2 プルタルコスとルクレティウスの証言―本文と分析
⑴ プルタルコス『倫理論集』九一八C
⑵ ルクレティウス『事物の本性について』Ⅳ六七九―六八〇 39
Ⅱ 「プルタルコス/ルクレティウスの格言」と禿鷲の言葉
1 「プルタルコス/ルクレティウスの格言」の伝承史の問題
2 「プルタルコス/ルクレティウスの格言」と禿鷲の言葉の差異
⑶ κενέβρεια, πτῶμα, σῶμα
⑷ γύψ とἀετός
⑶ πόρρωθεν/quamvis longe とὅπου (+ ἐάν)
⑷ まとめ
3 小 括
Ⅲ イエスの「神の国」のイメージ・ネットワークへ
1 新たな問いとその前提
⑴ Q資料における禿鷲の言葉の位置
⑵ 史的イエスの「人の子」と原始キリスト教会の「人の子」
2 生前のイエスの発言の可能性
3 判別の規準
Ⅳ Q資料からマタイとルカ福音書へ
1 マタイの解釈
2 ルカによる編集
第二章 神の国はあなたがたの〈内面に〉― ルカ福音書一七章
節の「エントス」ἐντός と禿鷲の言葉(ルカ一七)
要 旨
はじめに
Ⅰ 先行研究について
Ⅱ 本章の課題
Ⅲ ルカ福音書一七章20―37節における伝承と編集
1 ルカ福音書一七章23―37節の分析
⑴ ルカ福音書一七章37節は一七章24節と元来一体のもの
⑵ ルカ福音書による解釈
2 ルカ福音書一七章22節
⑴ ルカ福音書一七章37節と一七章22節の間の「囲い込み」構造
⑵ 「日々」の神学
⑶世界史の神学
〈補論〉 ルカの「世界史の神学」の研究史について
⑷ 脱終末論化
3 ルカ福音書一七章20―21節
4 ルカの解釈― ファリサイ人へのアイロニー
⑴ ルカ福音書全体の文脈との適合性
⑵ 史的イエスに向かっての問い返しとの区別
◇付記
Ⅳ トマス福音書語録三と一一三への影響史
第三章 ふたたびマルコ福音書四章12節の「メーポテ」μήποτε について ― 吉田忍氏へ十九年後の応答
はじめに
Ⅰ コイネー・ギリシア語における「メーポテ」μήποτε の事例
〈用法1〉 警告や命令などの後で否定目的節(あるいは結果節)を導く用法
〈用法2〉 蓋然的推量・否定的内容(危惧)の従属節または独立文を導く用法
〈用法3〉 蓋然的推量・積極的内容の従属節または独立文を導く用法
〈小 括〉
Ⅱ マルコ福音書四章12節の背後のアラム語(タルグム)伝承の問題
おわりに
第四章 「ナゾラ人」の系譜― 史的イエス研究の忘れ物
要 旨
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「ナゾラ人」(Ναζωραῖος)の語源の問題
Ⅲ 「ナゾラ人」の起源と広がり
1「遵守派」運動
⑴ エッセネ派
⑵ 砂漠の隠者バンヌース
⑶ テラペウタイ
⑷ クムラン教団
⑸ 原始マンダ教団と洗礼者ヨハネ
⑹ まとめと作業仮説
2 「ノーツリーム」の語義・「遵守派」
3 ヘブライ語からアラム語へ、そしてマンダ語へ
4 アラム語からギリシア語とシリア語へ
5 ラビのユダヤ教
⑴ 「アヴォダー・ザラー」一六b―一七a
⑵ 「ギッティーン」五七a
Ⅳ おわりに
第四章補論
マンダ教文書『ハラン・ガワイタ(内なるハラン)』
はじめに
1 邦訳の底本
2 英訳の原典
3 文書の内容
4 文書の伝承と編集
5 文書の成立年代と背景
6 思想的・文学的特徴
本文翻訳
写字生のまえがき
Ⅰ ユダヤ教支配下の時代(§ 2―13)
Ⅱ パルティア王国とササン朝ペルシア支配下の時代(§14―21)
Ⅲ イスラム教支配下の時代(§ 22 ―24)
Ⅳ ヒビル・ツィワの教え(25― 34 )
写字生のあとがき(§35―37)
英訳者のあとがき(§38)
第五章 「人の子」の肉を食べ、その血を飲む―ヨハネ福音書六章51b―58節と聖餐式
はじめに
Ⅰ 創世記の原初史
Ⅱ ヨハネ福音書六章51b―58節
Ⅲ 文化人類学の「贈与論」
Ⅳ シモーヌ・ヴェイユの聖餐論と「犠牲の思想」
1 「神を食べる」― 神の受難と犠牲
2 諸宗教の類例
3 「偽の犠牲」と「真の犠牲」
付 録 荒井献の学術研究― その功績と遺された課題(追悼講演)
著者紹介
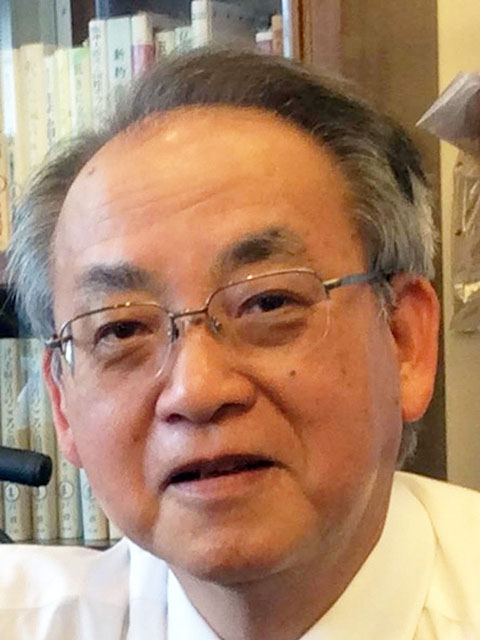
大貫 隆(おおぬき・たかし)
1945 年静岡県浜松市生まれ。1968 年一橋大学卒業、1972 年東京大学大学院人文科学研究科西洋古典学専攻修士課程修了、1979年ミュンヘン大学神学部修了・神学博士、1980 年東京大学大学院博士課程(前記)単位取得退学、東京女子大学専任講師、1991 年東京大学教養学部助教授、2009 年同名誉教授、自由学園最高学部長(—2014)。
主な著作:『世の光イエス ― ヨハネ福音書のイエス・キリスト』(1984 年、改訂増補版、1996 年)、『福音書と伝記文学』(1996 年)、『ロゴスとソフィア — ヨハネ福音書からグノーシスと初期教父への道』(2001)、『聖書の読み方』(2010)、『終末論の系譜 ― 初期ユダヤ教からグノーシスまで』(2019)、『イエスの「神の国」のイメージ ― ユダヤ主義キリスト教への影響史』(2021)、『ヨハネ福音書解釈の根本問題 ― ブルトマン学派とガダマーを読む』(2022)、『グノーシス研究拾遺 ― ナグ・ハマディ文書からヨナスまで』(2023)『原始キリスト教会の「贖罪信仰」の起源と変容』(2023、2024)著訳書多数。