焚き火を囲めるようなおとなになりたい!評者 藤本 満 師
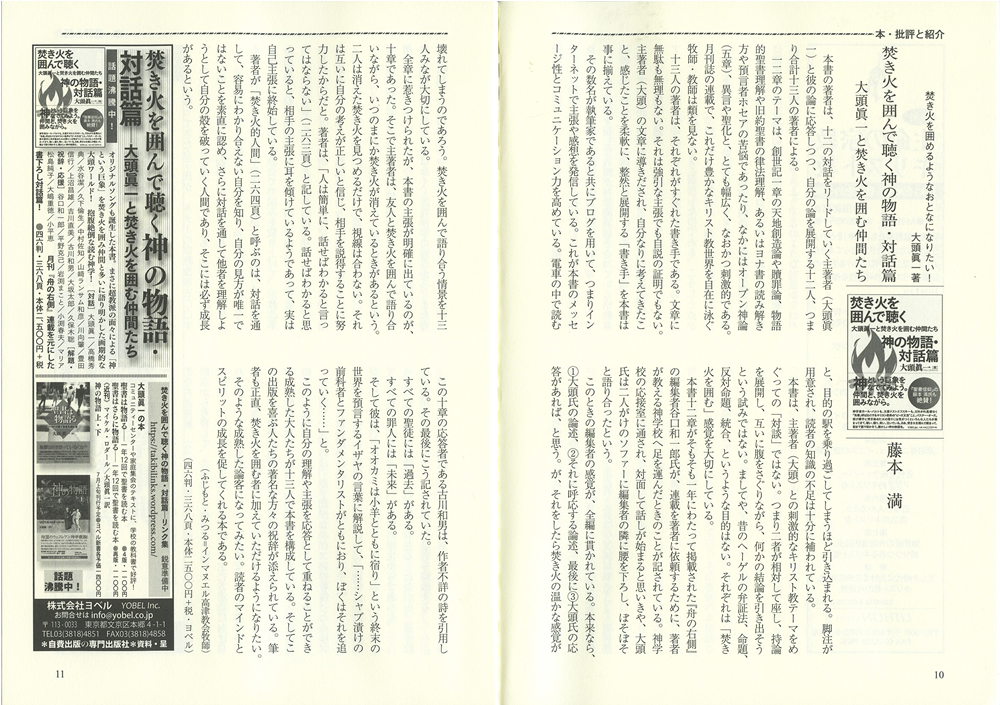
焚き火を囲んで聴く神の物語・対話篇 —— 大頭眞一と焚き火を囲む仲間たち
本書の著者は、十二の対話をリードしていく主著者(大頭眞一)と彼の論に応答しつつ、自分の論を展開する十二人、つまり合計十三人の著者による。
一二章のテーマは、創世記一章の天地創造論や贖罪論、物語的聖書理解や旧約聖書の律法理解、あるいはヨナ書の読み解き方や預言者ホセアの苦悩であったり、なかにはオープン神論(五章)、異言や聖化と、とても幅広く、なおかつ刺激的である。
月刊誌の連載で、これだけ豊かなキリスト教世界を自在に泳ぐ牧師・教師は類を見ない。
十三人の著者は、それぞれがすぐれた書き手である。文章に無駄も無理もない。それは強引な主張でも自説の証明でもない。
主著者(大頭)の文章に導きだされ、自分なりに考えてきたこと、感じたことを柔軟に、整然と展開す「書き手」を本書は見事に揃えている。
その数名が執筆家であると共にブログを用いて、つまりインターネットで主張や感想を発信している。これが本書のメッセージ性とコミュニケーション力を高めている。電車の中で読むと、目的の駅を乗り過ごしてしまうほど引き込まれる。脚注が用意され、読者の知識の不足は十分に補われている。
本書は、主著者(大頭)との刺激的なキリスト教テーマをめぐっての「対談」ではない。つまり二者が相対して座し、持論を展開し、互いに腹をさぐりながら、何かの結論を引き出そうという試みではない。ましてや、昔のヘーゲルの弁証法、命題、反対命題、統合、というような目的はない。それぞれは「焚き火を囲む」感覚を大切にしている。
本書十二章がそもそも一年にわたって掲載された『舟の右側』の編集者谷口和一郎氏が、連載を著者に依頼するために、著者が教える神学校へ足を運んだときのことが記されている。神学校の応接室に通され、対面して話しが始まると思いきや、大頭氏は二人がけのソファーに編集者の隣に腰を下ろし、ぼそぼそと語り合ったという。
このときの編集者の感覚が、全編に貫かれている。本来なら、
①大頭氏の論述、②それに呼応する論述、最後に③大頭氏の応答があれば、と思う。が、それをしたら焚き火の温かな感覚が壊れてしまうのであろう。焚き火を囲んで語り合う情景を十三人みなが大切にしている。
***
全章に惹きつけられたが、本書の主張が明確に出ているのが、十章であった。そこで主著者は、友人と焚き火を囲んで語り合いながら、いつのまにか焚き火が消えているときがあるという。二人は消えた焚き火を見つめるだけで、視線は合わない。それは互いに自分の考えが正しいと信じ、相手を説得することに努力したからだと。著者は、「人は簡単に、話せばわかると言ってはならない」(263頁) と記している。話せばわかると思っていると、相手の主張に耳を傾けているようであって、実は自己主張に終始している。
著者が「焚き火的人間」( 264頁) と呼ぶのは、対話を通して、容易にわかり合えない自分を知り、自分の見方が唯一ではないことを素直に認め、さらに対話を通して他者を理解しようとして自分の殻を破っていく人間であり、そこには必ず成長があるという。
この十章の応答者である古川和男は、作者不詳の詩を引用している。その最後にこう記されていた。
すべての聖徒には「過去」がある。
すべての罪人には「未来」がある。
そして彼は、「オオカミは小羊とともに宿り」という終末の世界を預言するイザヤの言葉に解説して、「……シャブ漬けの前科者とファンダメンタリストがともにおり、ぼくはそれを追っていく……」と。
このように、自分の理解や主張を応答として重ねることができる成熟した大人たちが十三人で本書を構成している。そしてこの出版を喜ぶ人たちの著名な方々の祝辞も添えられて。筆者も正直、焚き火を囲む者に加えていただけるようになりたい。
そのような成熟した論客になってみたい。読者のマインドとスピリットの成長を促してくれる本である。
(ふじもと・みつる=インマヌエル高津教会・牧師)



