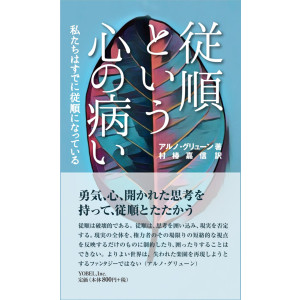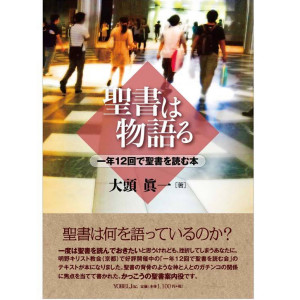《翻訳者のことば》グリューン著『従順という心の病い』を翻訳して〜村椿嘉信
スイスの心理学者アルノ・グリューン(1923―2015年)の『従順という心の病い』(原題『従順に抗して』2014年)を翻訳し、グリューンの『私は戦争のない世界を望む』と同じ出版社から出版した。彼は、その後、『テロリズムに抗して』、『冷たい理性に抗して』を書いている。
グリューンの晩年の一連の書物を読むと、彼が何を問題にしていたかがわかる。彼は、世界中に暴力やテロリズムが蔓延していることを憂慮し、その原因が欧米の帝国主義的な国家の中にあること、つまり私たちの文化の根底にある「客観的理性への崇拝」や「普遍的合理性という価値観」にあることを指摘した。私たち人間は、「理性的な熟慮」や「合理的な判断」に基づいて、もっとも野蛮な「戦争」やさまざまなかたちの「暴力」を起こすのである。彼はその問題性を、みずからの戦争体験(=ナチズム体験)や、精神病理学者としての臨床の知見から、心理学的に解明しようとした。
私は、沖縄で、まわりにいる人たちとともに歩みながら、私たちが生きている時代の問題や平和の問題、また人間の心の中のさまざまな問題に直面させられ、神学だけでなく、哲学、社会学、歴史学、政治(経済)学、心理学……などを学び続けてきた。その中で、従来の心理学や精神病理学関連の書物は、どちらかというと分析的で狭い分野を深めるには役立つが、今日における「個」としての人間の問題と、過去、歴史、社会、文化の問題を総合的に捕らえるには実際的ではないと思うようになった。グリューンを読んで、現実の問題に向き合って対話できる「心理学」とやっと出会ったと思わされた。
キリスト教は、聖書の言葉、主イエスについての教え、あるいは主イエス自身の教えを、どのようにとらえ、時代の中で混迷する人たちに伝えようとしているのか。戦争がテロというかたちでますます複雑化し、人間の生命の重さが軽んじられ、「他者」が信じられなくなる現代世界の中で、改めて神を「信仰」することがどういうことなのか、主イエスの「隣人愛」とはどのようなものなのかを、問い直す必要があるのではないか。
キリスト教の「信仰」は、神への「依存」や、主イエスへの「服従」であると言われる。しかしその場合の「従順」とは、従順であるという「人間的な姿勢や生き方」の問題なのだろうか。神に「従順」であるということは、「権威者」や「何らかの組織」あるいはその「決まりごと」に従順であるということとは、次元を異にする問題ではないか。
宗教改革者ルターは、『キリスト者の自由』という小冊子の中で、「キリスト者は、すべてのものに仕える僕(しもべ)であって、誰にでも服する」と主張したが、その場合の「服する」ということは、どういうことか。ルターは、この命題の前に、もう一つ「キリスト者は、すべての上に立つ自由な主人であって、だれにも服しない」という命題を対置したが、私たちはそのような自由に生きているだろうか。むしろグリューンの言うように、「私たちはすでに(この世の支配者や、支配的な価値観に)従順になっている」のではないか。
日本のキリスト教は、一方において、神に「従順」になるように教え、他方において、教会(の伝統や制度、信仰理解)に、さらには家庭に、社会に、国家に「従順」になることを要求してきたのではないか。キリスト者は、日本という社会の中で、社会が要求する奉仕活動(ボランティア活動、社会福祉)を行うことがあっても、この世の秩序や価値観に「従順」であり続けているのではないか。その結果、主イエスの実践や教えから大きく逸脱し、みずからの実存的ならびに歴史的な罪責を覆い隠し、自分の中にある「神から一人ひとりに与えられた独自なもの」を拒否し、自分とは違う「異質なもの」に攻撃的になっているのではないか。私たちがコピーとして生きることをやめ、愛をもって他者に出会い、ともに助け合って生きるために、グリューンの心理学は、さまざまな示唆を与えてくれる。
(ぎのわん日曜集会、日本基督教団牧師)